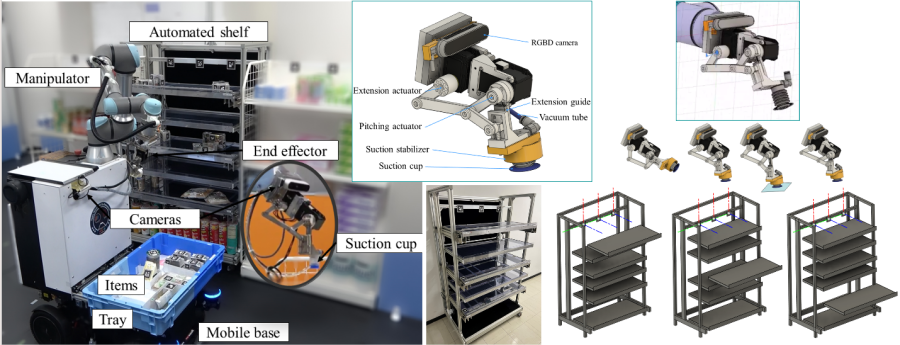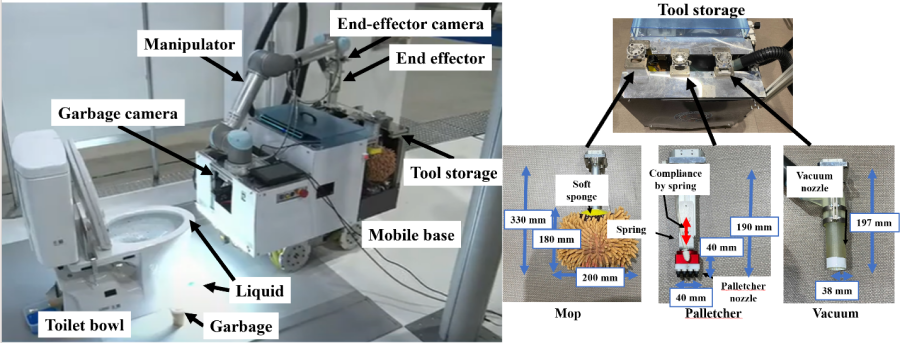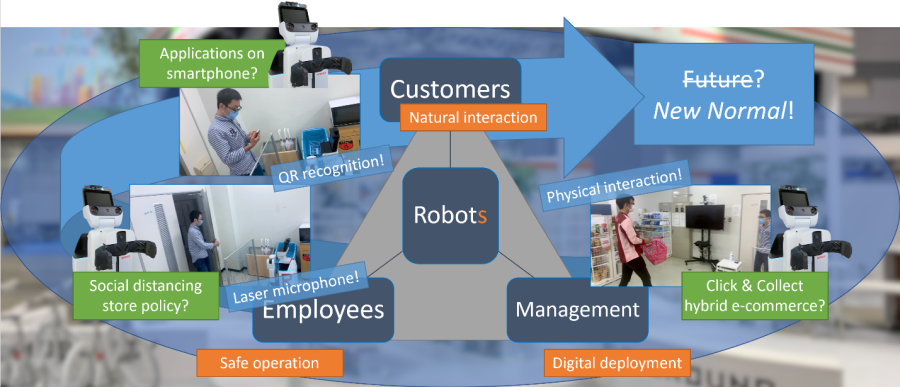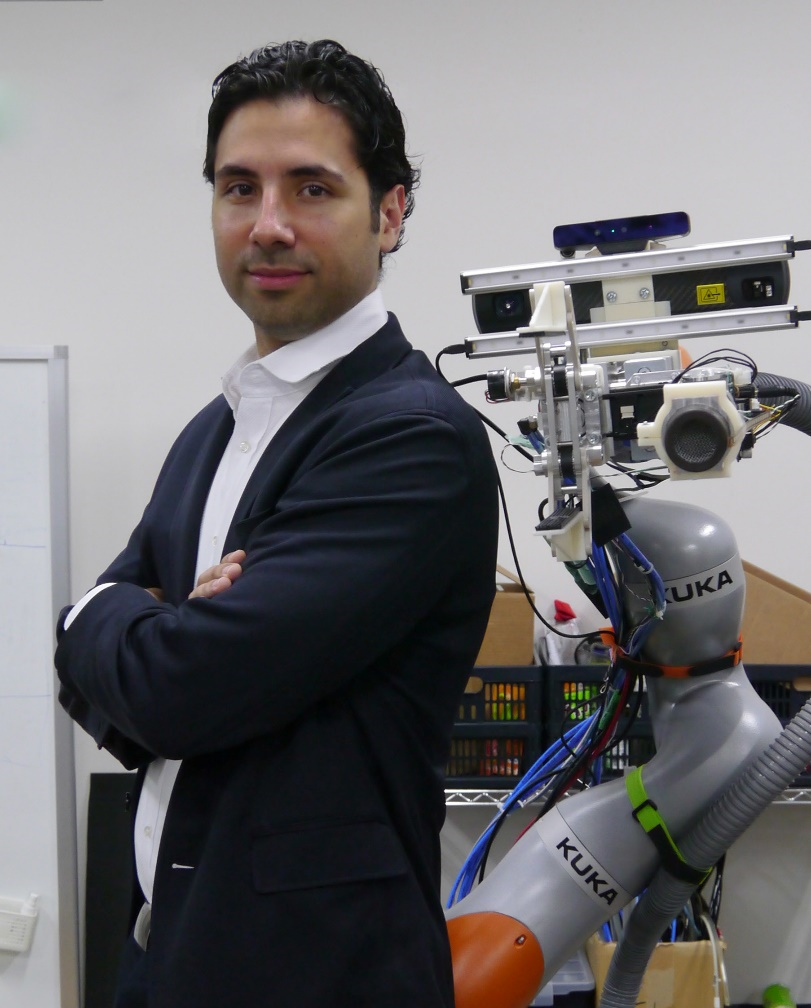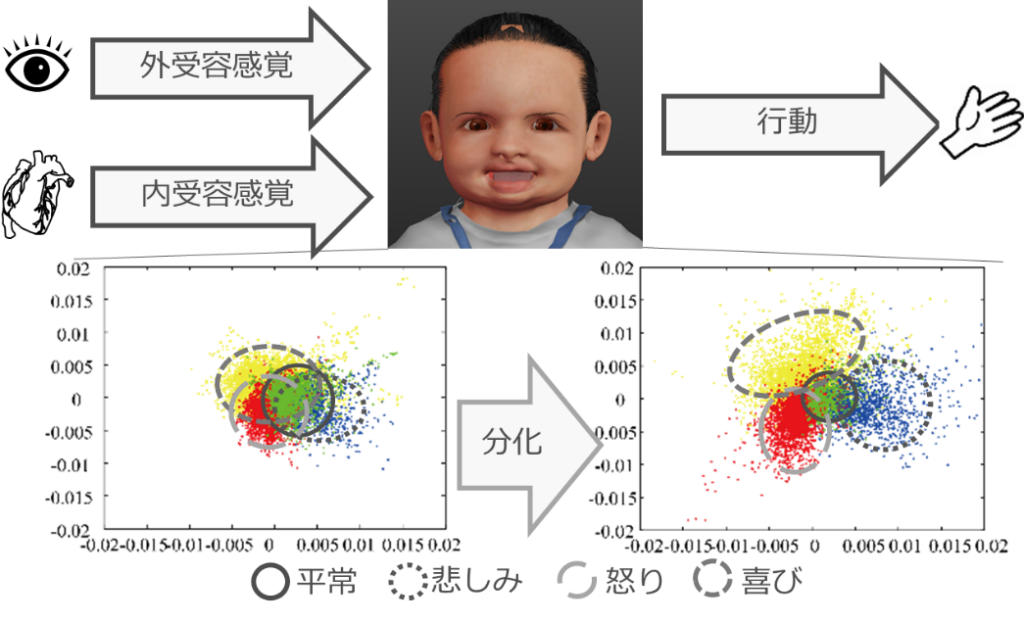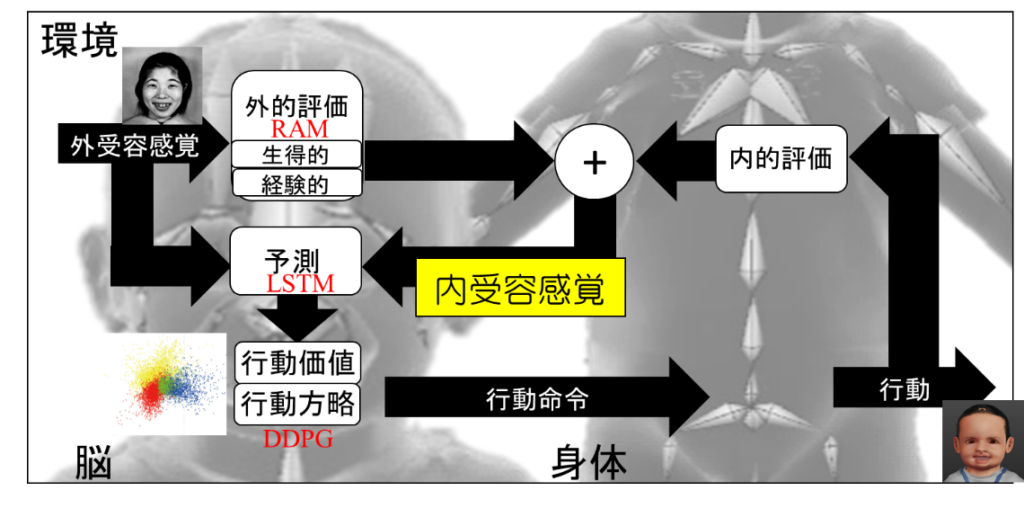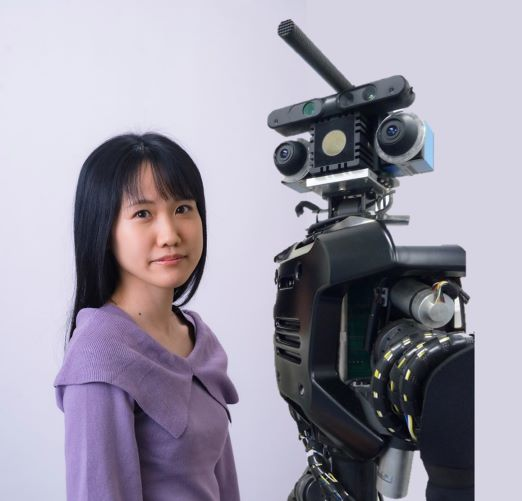導入
情報科学領域ヒューマンロボティクス研究室助教の織田です.私は,屋外や自然環境で動作するロボットのための技術―フィールドロボティクス―に関する研究を行っている.現在は,水中ビークル,四足歩行ロボット,1人乗り用電動車椅子型ビークルといった実際のロボット/ビークルプラットフォームの自動化によって,リソース不足で困っている人や危険で負担の大きい作業に従事している人々の助けになりたいという想いで研究している.本稿では,水中ビークルに関する研究について紹介する.
1.社会的背景
湾港施設をはじめとする多様な水中構造物は劣化が激しく,定期的な検査を必要としている.現状は点検作業の多くを潜水士に頼っているが,水中での作業は潜水士にとって危険を伴うものであり,肉体的・精神的負荷が高い.
近年,ROV(Remotely Operated underwater Vehicle)と呼ばれる小型・軽量で遠隔操縦型の水中ビークルが市販されるようになった.比較的安価でありながら一定の拡張性を併せ持ち,様々な水中での作業に活用できる可能性があるため,潜水士の代替としても期待されている.我々が実際に研究で使用している機体を紹介する(図1,図2).市販のROVをベースに特定の作業に対応できるように改造・拡張が施されているが,この程度であれば当時素人であった著者自身でもなんとかなった.ROVの特徴として,テザーケーブルと呼ばれる100m~数100m級の操縦者とROV間の通信用ケーブルが装備される.実際には,さらにグリッパやマニピュレータが装着される例も多い.ROVを活用することで,水中インフラの検査だけでなく,海底遺跡の調査や海洋資源の採取,生態系のモニタリング,さらには養殖管理に至るまで,学術的な探究にとどまらず社会課題の解決にも貢献が期待できる.


2.水中ロボット/小型・軽量ROVの難しさ
潜水士に代わりROVを導入すれば問題が解決されるわけではない.効率的に作業を進めるには,ROV遠隔操縦の難しさを克服する必要がある.一般的な操縦時の難しさとして以下の2点挙げる.
- 操縦の複雑さ
ROVは3次元空間での運動になるので,並進3自由度(x, y, z)と回転3自由度(roll, pitch, yaw)の合計6自由度を同時に制御する必要があり,操縦が非常に複雑である.その上で,操縦者の入力どおりにROVが動作するとは限らない.軽量・軽量の機体は外力・外乱の影響を受けやすく,機体の表面形状によっては水流(潮流,乱流を含む)の影響が大きく増大する.加えて,浮心と重心のずれに起因する復原力や,テザーケーブルからの張力もROVの運動に大きな影響を及ぼす.これらすべての外力・外乱の影響を操縦中に正確に把握することは不可能に近く,それらを打ち消すように操縦することもまた困難である.テザーケーブルに関しては、水中構造物との絡まり問題も頭の片隅に置いておく必要がある. - 酔い
特に船上からの操縦では,船酔い・操縦酔いと闘う必要がある.著者の印象・経験上ではあるが,グリッパで物体を掴むといった数センチ単位の操縦精度を要する作業や,濁った映像から特定の物体を探し出すように画面を注視する作業では,酔いの症状の進行が非常に早い(図3).熟練操縦者であっても決して簡単な仕事ではない.
上記の操縦時の難しさ・負担を軽減させるために,自動化技術を活用した支援策が議論されている.続いて,小型・軽量ROVの自動化技術活用に関連する難しさを4つの項目に分けて整理する. - 自己位置推定問題
一番の問題は,信頼できる自己位置推定手法が確立されていない.水中ではGNSS(Global Navigate Satellite System)が利用できない.IMU(Inertial Measurement Unit)やDVL(Doppler Velocity Log)を用いた手法は,一般的に位置・姿勢の推定値がドリフトする.大域的な位置・姿勢推定が現状困難であり,ROV自身が,自分がどこにいてどういう状態なのか正確に推定することが難しい. - センサ種類・センサ数制限
ROVに搭載できる環境計測用のセンサの選択肢が大きく制限される.水中では電磁波が著しく減衰するためである.近距離計測では光学的手法も利用されるが,主流はソナーセンサに代表される音響計測である.
また,コスト上昇,機体の大型化につながるセンサ数の増加は望ましくない.小型・軽量ROVの運用上の手軽さという大きな利点を失うからである.各センサには視野角,計測可能レンジ,分解能,解像度といった制約がある中で,センサ数も制限される.さらにセンサ系は,水中の濁りの程度やROVの急な姿勢変化の影響も受けるため,設計段階でうまく制約を補っていたとしても,期待された性能を常に発揮するとは限らない. - モデルの不確実性
環境変化や機体改造によるモデルパラメータの変動,浮力調整のための浮力材・バラスト着脱による浮心・重心位置の微妙な移動,スラスタの経年劣化による推力バランスの乱れは,正確なモデル化・パラメータ同定が困難である.さらに,テザーケーブルの運動モデリングの表現力の向上も必要である(図4,図5からも分かるが捩れや巻き癖などかなり不規則). - 計算機の問題
機体そのものが小さいため搭載できる計算機が低性能になる.図2で示したように,耐圧容器の体積の関係でRaspberry pi,Jetson nano程度の計算機となる.たとえ多数のセンサを装着することができても,それらを処理できる性能の計算機を載せることが難しい.
以上のように,本稿で取り上げられるだけでも,水中環境や機体に由来する,シミュレーションでは再現が難しい,あるいは無視されがちな実際的な問題や制約が存在することが分かるだろう.

3.自動化
ここでは,センサ系が期待通りに機能する環境下での,制御精度そのものを向上させるための研究を紹介する.
1つ目が,対象物の前で位置・姿勢を維持し,対象物をカメラに捉え続ける定点保持と呼ばれるシナリオである.しかし,前述のように,モデル,パラメータは不確実性が大きく,外乱も予測できない.そこで,入力に関するあるクラスの不確定性にロバスト性を有する逆最適制御を実装した.そして,proving groundでの実験として,NAISTの情報科学領域棟の屋外に設置されているプール設備で実験を行った(図4).静水中であれば前後・左右方向にそれぞれに目標点から誤差5cm以内,深度方向に10cm以内,角度誤差10deg以内で制御可能であることを確認した.この精度は,人間による遠隔操縦では達成が難しい精度である.
2つ目が,水流下での定点保持である.NAISTのプール設備は流水を発生させることが可能であり,学内でより実践的な検証が可能である(図5).BlueROV2をベースにした機体では,一定方向からのわずかな水流でさえも制御性能を大きく低下させることが実験により分かった.現在,流水下でも制御精度を維持できるROVの新たな制御手法を研究中である.
最後に,和歌山県広川町の湾港で実験を行った経路追従制御を紹介する(図6).これは,防波堤や船体に沿うように移動し,表面の検査を行うことを想定したシナリオである.図1に示したように,2個の1Dソナーセンサと深度(圧力)センサのみで,実環境で4自由度(x, y, z, yaw)の制御が可能である.湾港内の穏やかな海面状況ではあったが,テザー張力を受けながらも防波堤との間隔を目標値から誤差5cm以内,深度方向に誤差5cm以内,角度誤差10deg以内の精度を維持して,3分間程度壁に沿って自動航行できることを確認した.
現在は水中構造物の目視検査を想定したシナリオ設定・精度設定であるが,近い将来,物体把持等の環境との接触を伴う作業が可能な精度まで高めていきたい.



4.自動化技術を用いた操縦支援
理想的な環境下では,自動化によって前節で示した精度が得られる.しかし実際には,センサ系に大きな制約があり,自動化システムが機能する状況は限定的であるため,現時点での完全自動化は困難である.操縦負担の軽減や制御精度の向上を図るためには,自動化システムが機能する状況ではそれに任せ,機能しない状況で人間が介入・引き継ぐようなシステム設計が適切だと考えている.
このような自動化システムと人間の引き継ぎを滑らかに実現する枠組みとして,Shared Controlがある.中でも我々は,HSC(Haptic Shared Control)に注目している.我々のHSCの適用例を示す(図7). HSCにおいては,操縦者が手や腕を介して,ロボットの制御支援・意図・状態を触覚的に感じ取ることができる.したがって,ジョイスティックを単なる操作入力端末としてだけでなく,情報伝達の媒体としても扱うことが可能である.
我々は,これを人間が操縦を引き継ぐべきタイミングの伝達に応用した.具体的には,人間による介入が不要な状況では,ジョイスティックを人の力では動きにくく設定し,介入が必要な状況では動かしやすく設定した.これは,操縦者がセンサ系や自動化システムの挙動を深く理解していない場合でも,センサ系の限界を直感的に把握でき,適切なタイミングでの引き継ぎを可能とすることを目的としている.また,人間とシステムが制御入力端末を共有するHSCでは,人間が意図せず制御精度を損ねたり,自動化システムの動作を妨げたりするリスクがある.自動化システムが機能している間,入力端末そのものを人間の力では動かしにくくし,人間に邪魔をさせないという設計意図も含まれる.20名の実験参加者による評価をNAISTプール施設で行った.本稿の読者の中にも,ROV操縦の難しさを体験した人が含まれているでしょう.

5.研究に対するアプローチ
私の研究チームでは,実際のものに触れ,可能な限り実践的な環境で実験することを意識している.1つの要素技術だけでなく,我々が向き合っている課題全体を俯瞰的に見るためである.これにより,自身の研究が最終的なアプリケーション,目的に対してどれほど貢献できるかの評価,および実際のプラットフォーム,実環境でしか見つけられない問題の発見につながる.実環境で起こる現象を見て・体感して,どんな問題があり,何を解くべきか目的から逆算して考える.これはまだAIには難しいと思っている.
一方で,便利なシミュレータが登場し,人がそちらへ流れている.ただし,シミュレーションは実世界すべてを表現できないのは先述の通りで,特に水中ロボティクスでは,使用するシミュレータと実環境の一致性に言及する必要があるだろう.シミュレータ上で得られた進展が実世界での進展としてどの程度に相当するのか,実世界での問題解決にどれほど近づいたかしっかり議論する必要があるだろう.私たちの目的は常に実世界にあるからだ.また,シミュレーションは,MCP(Model Context Protocol)の発展などにより,近い将来すべてAIでできてしまう可能性が高いだろう.
最後に少しROVの話に戻ると,市販の小型・軽量ROVは,多くの制約の中での運用となるので,1つの機体に多くの機能は搭載せず,1機体1機能のような考え方が現実的ではないかと思う.また,現存の環境にそのままROVを導入しようとすると難しい局面も多く,ROVの活用を前提として,環境にも手を加えていく必要があるのではと考えている.
著者紹介
織田 泰彰
立命館大学大学院 博士(工学).2022年4月より奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 助教.学生時代は,消防隊員を自動追従し資機材運搬の支援を行う半自律クローラ型移動ロボットに関する研究に従事.専門はフィールドロボティクス.非線形制御理論,ロボットビジョン,それらの実機・実践的環境での応用を主軸として,現在はHuman-Automation collaborationの研究にも従事.イングランドのフットボールクラブLiverpool FCのファン.
Webサイト:https://researchmap.jp/yskorita